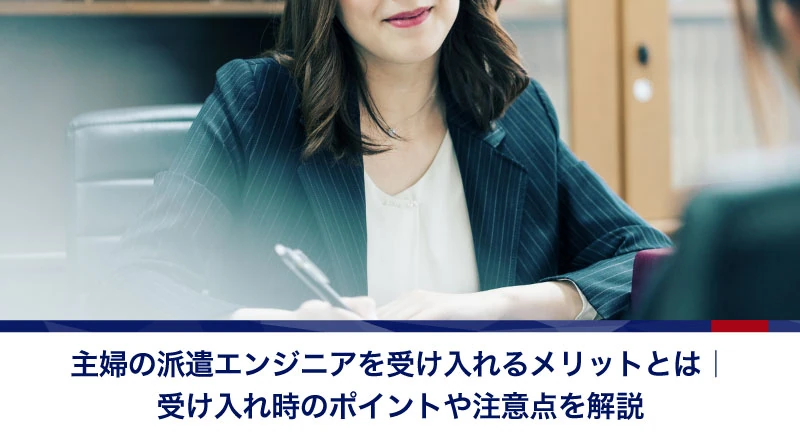SIerと下請けの違いとは?多重下請け構造が生じる理由や問題点も解説
SIerは、IT人材が不足している企業にとって頼りになる存在です。しかし、SIerとはどのようなものなのか、いわゆる「下請け」と呼ばれるポジションとは異なるのかを、いまいち理解しきれていない人も多いでしょう。本記事では、SIerと下請けの概要や、それぞれの違いを解説します。SIerの多重下請け構造についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
Contents
SIerとは?
まずは、SIerの定義や役割から解説します。
SIerの定義
SIer(エスアイヤー)とは、System Integrator(システムインテグレーター)の略称です。顧客の要望に応じて、システム開発や運用・保守、コンサルティングなどを担うサービスや企業を指します。システムベンダーやITベンダーと呼ばれることもあるでしょう。SIerの業務内容は多岐にわたり、顧客の要望に応じてさまざまな仕事を請け負います。
SIerの役割
SIerの主な役割は、必要な人材が不足している企業に代わって、システム開発や運用・保守などのIT業務を担うことです。要件定義から運用・保守までの全工程を一括で依頼できる他、一部の工程のみを任せることも可能です。また、単なるIT業務の受託にとどまらず、顧客のビジネスの成長をサポートする役割を担うこともあります。
SIerの5つの種類
SIerは、下記の5種類に分けられます。
- メーカー系
- ユーザー系
- 外資系
- 独立系
- コンサル系
それぞれの特徴は、次のとおりです。
1.メーカー系
メーカー系SIerは、IT関連機器を製造販売するメーカーの情報システム部門が、系列会社として独立したケースが多いでしょう。基本的には、親会社のIT関連機器と組み合わせたサービスを提供します。
2.ユーザー系
ユーザー系SIerは、IT関連機器以外の企業(金融・商社など)のシステム部門が独立した業態です。親会社だけでなく、他社からの依頼も受けます。
3.外資系
外資系SIerは、グローバル展開をしている企業の日本法人として、海外のパッケージやソリューションを国内に導入します。また、コンサルティングに強い企業も多い点も特徴です。
4.独立系
親会社を持たないSIerのことを、独立系SIerと呼びます。メーカーやベンダーにとらわれないサービスを提供しており、柔軟な対応が魅力です。
5.コンサル系
コンサル系SIerは、上流工程のITコンサルティングを主な業務としています。経営戦略やIT戦略などのコンサルティングを入口として、システム開発といったIT業務も手がけます。
下請けとは?
下請けとは、ある企業が受注した仕事を、また別の企業や個人が引き受けることです。基本的には、大企業が仕事を受注し、中小企業が下請けとなるケースが多いでしょう。単発的な受発注ではなく、持続的なつながりを持つ点も特徴です。
下請けと元請けの違い
発注者から最初に仕事を受注した事業者を「元請け」と呼びます。一方、下請けは、元請けから仕事を受ける事業者を指します。
IT業界における下請け構造の具体例
ここからは、IT業界における下請け構造の具体例を紹介します。
1次請け
1次請けとは、発注者から最初に仕事を受けた事業者、つまり元請けのことです。発注者と直接打ち合わせをするほか、プロジェクトを管理する役割を担います。
2次請け
2次請けとは、1次請け(元請け)から仕事を受注した下請け事業者のことです。元請けが発注者とともに作成した仕様書や設計書などに基づき、業務を進める役割を担います。
3次請け
3次請けとは、2次請けからさらに仕事を受注した事業者のことです。孫請けとも呼ばれ、IT業界では3次請けの労働人口が最も多いとされています。
SIerと下請けの違いとは
SIerは、「製薬会社」や「ハウスメーカー」のように企業の種類を表します。対して、下請けは、受発注における構造上の階層を意味します。
そのため、発注者との関係によっては、SIerが元請けになることもあれば、下請けになることもあるでしょう。なお、基本的には、大手SIerが元請け、中小SIerが下請けになるケースが大半です。
SIerの多重下請け構造とは
前述のように、元請けのSIerが受注した仕事を2次請けが引き受け、2次請けからさらに3次請けというように、段階的に下請けが発注するピラミッド構造のことを多重下請け構造といいます。大規模なプロジェクトになると、4次請け、5次請けと、委託が繰り返されるケースもあるでしょう。
なお、多重下請け構造はIT業界だけでなく建設業界や運送業界でも多いとされています。
多重下請け構造が生じる理由
多重下請け構造が生じる理由は、主に次の2つです。
人件費や人材配置のロスを削減するため
発注者から受けた案件を元請けの従業員だけで対応するためには、多くの人員が必要です。必要な人員を自社で確保するためには、当然のことながら多くのコストがかかります。そのうえ、案件の終了後には、人員リソースに余剰が生まれる可能性もあります。
そのため、元請けとしては、人材を自社採用するよりも、必要なときに必要な人材を確保する方がメリットが大きいといえるでしょう。これは、元請けだけでなく、2次請け、3次請けにもいえることです。
このように、自社だけでは対応しきれず業務委託が繰り返されることで、多重下請け構造が発生します。
大手と中小のパワーバランスが根付いているため
IT業界には中小企業が多くありますが、ユーザーの発注は大手企業に偏りがちです。そのため、上流は大手に独占されやすく、中小企業は単価が低くても元請けから仕事を引き受けなければならない状況に陥ります。こうしたパワーバランスが根づいてしまっていることも、多重下請け構造を生む原因となっています。
多重下請け構造の問題点
多重下請け構造の問題点は、次の4つです。
責任の所在が不明確になる
多重下請け構造では、下請けへの発注を繰り返すうちに認識の齟齬が生まれ、成果物が発注者の要望に沿わないものになることがあります。
しかし、多重下請け構造はプロセスが細分化されるので、責任の所在が不明確になりがちです。また、パワーバランスとしては下請けの方が劣勢になりやすく、責任を押しつけられやすいという問題もあります。
人材教育が成り立ちにくい
多重下請け構造は、下層にいくほど業務が細かく切り分けられ、単純作業がメインになる傾向があります。その結果、下請けほどスキル習得が難しい環境になってしまう点も問題です。
下請けの労働環境が悪化しやすい
なかには、下層の事業者に業務のほとんどを押しつける悪質な企業もあり、下請け事業者の労働環境が悪化する原因となっています。また、再委託が増えるたびに中間マージンが発生するため、下層にいくほど利益は少なくなってしまうものです。結果として、上層と下層とでは、労働者の賃金にも差が生じてしまいます。
市場競争力の低下を招く
多重下請け構造による待遇格差があると、下請け事業者の労働者が疲弊し、生産性の低下を招いてしまう場合があります。生産性の低い状態が続けば、市場全体における競争力の低下にもつながりかねません。生産性が低下することで成果物の品質が下がり、労働環境が悪化して生産性が下がる、という悪循環に陥るリスクもあります。
多重下請け構造を脱却するメリット
多重下請け構造を脱却すると次のようなメリットを期待できます。
開発品質やスピードが向上する
内製化によりすべての工程を自社で完結できれば、より綿密なコミュニケーションが実現します。情報共有やフィードバックなどもスムーズにできるため、開発スピードの向上につながるでしょう。また、意見交換や認識のすり合わせがしやすくなることで、開発品質の向上にも期待できます。
自社にナレッジを蓄積できる
外注を繰り返す構造は業務が細分化されやすく、社内に知見が蓄積されにくい側面があります。多重下請け構造を脱却して内製化を進めれば、プロジェクトでの課題や解決策を自社のナレッジとして蓄積することが可能です。さまざまなノウハウが蓄積されていくことで、次回以降のプロジェクトに役立つだけでなく、優秀な人材の育成にもつながります。
多重下請け構造から脱却するには?
ここからは、多重下請け構造を脱却する方法について解説します。
IT人材を確保する
多重下請け構造は、自社の人的リソースが不足しており、業務に対応しきれない場合に起きやすい傾向があります。これまで下請けに任せてきた業務のすべてを自社で対応するためには、優秀な人材を一定数確保しなければなりません。また、単に採用数を増やすだけでなく、育成に力を入れることも重要です。
人材確保が難しい場合は「ITエンジニア派遣サービス」もおすすめ
多重下請け構造からの脱却には人材確保が不可欠であるにも関わらず、日本ではあらゆる業界においてIT人材が不足しています。人材確保が難しい場合は、ITエンジニア派遣サービスの活用もおすすめです。
ITエンジニア派遣サービスとは、ITエンジニアの派遣に特化した人材派遣サービスのことです。採用コストや教育コストを軽減しながら、必要なスキルや経験を持つ人材を確保することができます。
人材派遣では派遣先企業に指揮命令権が認められています。ITエンジニアへの直接指示も可能なので、業務をスムーズに進められるでしょう。
まとめ
SIerとは、クライアントの要望に応じてシステム開発や運用・保守などのIT業務を行うサービスや企業のことです。一方、下請けとは、ある事業者が受注した仕事を、また別の事業者が引き受けることをいいます。
IT業界は元請けが受注した仕事を2次請けへ、2次請けが受注した仕事を3次請けへと、何重にも下請けが発生する「多重下請け構造」に陥りがちです。多重下請け構造はデメリットが多いため、自社のIT人材を拡充するなどして、脱却を図ることが望ましいでしょう。
ITエンジニアの自社採用が難しい場合は、ITエンジニア派遣サービスの活用もおすすめです。もし、ITインフラ領域での人材獲得にお悩みなら、アイエスエフネットのITインフラエンジニア派遣サービスをご活用ください。
アイエスエフネットのITインフラエンジニア派遣サービスは、ITインフラサービス専門としては最大級の規模を誇る人材派遣サービスです。ITエンジニアの教育投資やバックサポートにも力を入れており、課題に合わせた質の高い人材を提供いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
アイエスエフネットのITインフラエンジニア派遣サービスの問い合わせはこちら
よく読まれている記事
IT人材不足をまるっと解決!